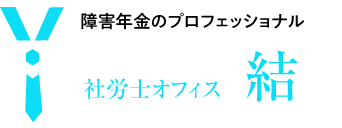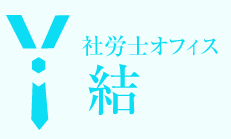-
-
不服申立てのススメ② 等級内の軽重|名古屋市の障害年金は社労士オフィス結
-
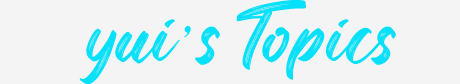
新着情報・ブログ
-
2022 / 09 / 06
不服申立てのススメ② 等級内の軽重
まず大雑把に私の思考を説明します。
障害年金の仕組みを簡単に理解するには一本のラインでイメージすることを説明しましたが、
障害等級をイメージする場合も以下のようなラインをイメージします。
3級 2級 1級
軽ー-----重軽------重軽------重
同じ2級でもその中で症状の軽い重いが存在します。
障害状態2級
軽ー---------ー--重
例えば精神疾患の場合には、
食事や保清、社会性などの日常生活能力の4段階の判定数値の平均と
全体的な日常生活能力の程度の5段階の数値で
等級の目安が決められています(※精神判定ガイドラインによる)が、
2級に該当する可能性のある範囲として、
軽いもの 判定2.0以上 程度 3 ー--
~重いもの 判定3.5以下 程度 5 ー--
このようにかなり軽重が広範囲にわたります。
障害等級の判定は認定基準を基に審査されるのだが、
認定基準においては私が考えるに、
重い状態を表すー--に該当するような状態を等級に該当する例示と設定している内容となっているので、
例示に該当しないー---な範囲を等級の障害状態には該当しない、と審査されることが多いと感じている。
これに対して不服申立てをする際2つのパターンがある。
一つは請求人の障害状態が重い状態ー--であると主張する方法
もう一つが軽い状態ー--でも障害等級に該当するはずだと主張する方法で、
私は断然に後者です。
前者の場合には、主治医に
「請求者の家での状態とかは本当はもっと悪いんですけど今まで伝えてなかったんですぅ」
とか説明して重い診断書を用意したりするんですけど、
それってどうなんだ?と思います。
患者の家での状態も当然に考慮している可能性もあるし、
患者が自分の本当の症状を自分に今まで伝えてなかったということは、信頼関係がないのか?
と思わせる事にもなりかねない。
それに、審査する側にー--の状態こそが等級該当状態で、
それ以外ー--は不該当に審査すのが当然
といった印象や実績を与えることになり、
等級該当状態のハードルが上がってしまう危険性があるんですよ。
なので私は診断書の状態が軽くても等級該当範囲に引っかかっていれば
それを主張する手法をずっと採ってきたわけです。
だから成功率が低いのかもしれないけど、、、
でも自分は間違ってないと思う。
今後もこの思考に沿った形で、不服申立てにおける
国の主張と自分の主張を書いていこうと思います。
続く
前の記事
不服申立てのススメ① はじめに
この記事を読んだあなたに
おすすめの記事
-
カテゴリー
最新のニュース
カレンダー
2026年2月 月 火 水 木 金 土 日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
-

社労士オフィス結
名古屋市中区錦二丁目17番11号
伏見山京ビルUS-SOHO伏見207
Copyright © 社労士オフィス結 All Rights Reserved.