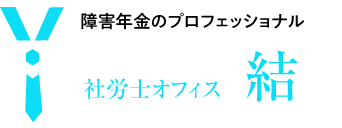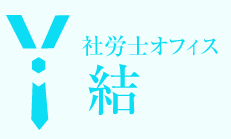-
-
障害年金は難しい?⑯ 第2段階-4 障害と傷病をつなぐ|名古屋市の障害年金は社労士オフィス結
-
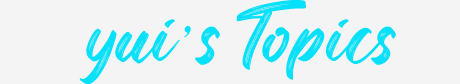
新着情報・ブログ
-
2022 / 07 / 08
障害年金は難しい?⑯ 第2段階-4 障害と傷病をつなぐ
前回まで
抱えている障害についてアプローチ
併合の可能性やどちらかが認められる可能性など検討し、
1種類の診断書を用意するか複数種類の診断書を用意するかで、単独障害か複数障害か がまず決まる。
今回はその障害と原因となった傷病について検討していきます。
肢体障害と精神障害の2つの障害を抱えているとします。
その原因は両障害とも脳梗塞であると説明を受けます。
この段階では
脳梗塞ー---------肢体障害・精神障害
という単独傷病で複数障害 の骨格と考えられますが、
前回は障害について先にアプローチしましたが、
今度は傷病についてのアプローチをしなければなりません。
具体的には既往症を確認するなど過去に診断された病名などを検証していく作業です。
その結果、今回の脳梗塞の数年前に軽い脳梗塞があったとします。
軽い脳梗塞①ー---今回の脳梗塞②ー--------ー肢体障害A・精神障害B
①と②が相当因果関係があると判断したならば
①と②それとつながるAとBは同一のライン上にあるから、
単独傷病で複数障害 のタイプで変更ありません
※初診日は①傷病時点に変わります。
しかし、①と②は因果関係のない別傷病と判断されれば、
①と②はつながらなくなります。
しかもAとBの障害状態については②の傷病だけによるものではなく、
軽い症状だったかもしれないが①の影響も考えられます
方程式のように表現すると
①傷病+②傷病=A+Bの障害状態
②傷病だけ=A+Bの障害状態-①傷病の影響
正確にA+Bの障害状態を判定してもらうには、
複数傷病で複数障害の骨格で請求することになります。
軽い脳梗塞①☓因果関係なし☓今回の脳梗塞②ー---------肢体障害A・精神障害B
難しく思われるかもしれませんが、
基本はずっと同じです
障害には必ず原因となった傷病がある
原因となった傷病と現在の障害は一本のライン上にある
障害の状態イコール全てその原因傷病によるもの
つまり 傷病=障害の等式が成立
この基本構造には何ら変わりはありません。
ちなみに傷病からアプローチする場合には
メインと思われる傷病名を中心に過去に診断された病名や既往症を確認し、
それらが同一ラインか別傷病なのかを検証し、
その各傷病に現在の障害状態をつなぎ合わせていくものですから、
結果的には同じになるはずですから、障害が先でも傷病が先でもどちらでもよいと思います。
これは例えば作詞作曲をする場合に、
どちらを先にしなければいけないと決まっているわけではない事と同じです(知らんけど)
続く
この記事を読んだあなたに
おすすめの記事
-
カテゴリー
最新のニュース
カレンダー
-

社労士オフィス結
名古屋市中区錦二丁目17番11号
伏見山京ビルUS-SOHO伏見207
Copyright © 社労士オフィス結 All Rights Reserved.